個々の性格診断から人間関係を科学的に分析し、最適な組織編成・開発に応用する『FFS理論』にて、数多の組織・人材の活性化を支援してきた古野俊幸氏。この理論をベースに人気漫画の登場人物を題材に解説した「宇宙兄弟とFFS理論が教えてくれる あなたの知らないあなたの強み」に続き、4月には「勉強の型」を指南する『ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる あなたが伸びる学び型』を上梓した。企業だけでなくプロ、大学スポーツの組織編成も支援してきたエキスパートが、FFS理論をベースにスポーツから日常に応用できる自己分析、チーム編成の考え方を連載形式でお届けする。
サッカーには「ディフェンス」や「ミッドフィルダー」というポジションがあります。しかし、全てのディフェンス、ミッドフィルダーが同じように動いている訳ではありません。攻撃参加を得意としている選手もいれば、守りに比重が置かれている選手もいます。位置的には「中盤」であるミッドフィルダーも同様に攻撃的と守備的に分けられます。もちろんチーム事情で〝役割として担う〟ケースもありますが、監督は選手個々の『得意』を見抜いて抜擢するケースの方が多いのです。
特にサッカーのように『監督がチーム作りの全てを決める』場合、監督自身がポジション毎に求める役割、動きがあり、それを担えそうな選手を探して抜擢しています。
その意味で、自分は「何が得意か」を明確に理解し、それを日々磨いている選手は、監督に見染められる可能性があり、そうでない選手は、〝器用貧乏〟としてそこそこで終わってしまう恐れがあります。つまり「一芸に秀でる」ことは単に目立つだけでなく、チーム作りの〝重要なピース〟となるのです。もちろん「ユーティリティプレーヤー」も必要ですが、それは〝ユーテリティ〟としての一芸レベルでしょう。
この「自らの得意を理解している」テーマをビジネスシーンで考えてみましょう。
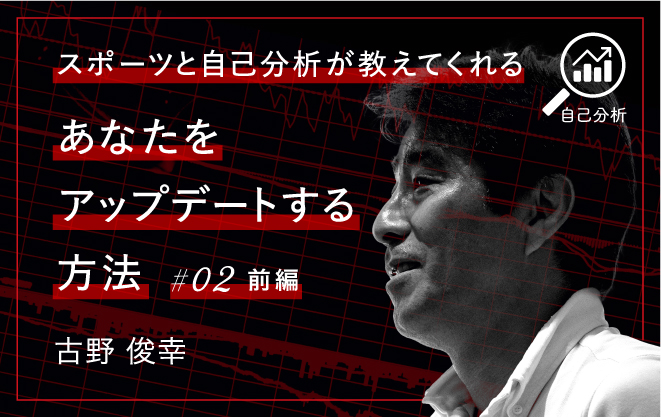
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜