アスリートの競技成果を向上させる座学プログラムを、ビジネスなどあらゆる分野の人材育成メソッドに体系化した「スティッキー・ラーニング」を開発した坂井伸一郎氏。「絞って伝えて、反復させること」をポイントに、多業種のビジネスパーソンを 「戦力」に変えてきた人材育成のプロが、時代の変化に適応するチームビルディングの在り方について、連載でお届けしていく。
目次
村井チェアマンも重要視する「コンセプトの共有」
こんにちは、坂井伸一郎です。アスリート育成に倣う「新時代のチームビルディング」ということでコラムを書かせていただいております。今回も臨時チームで成果を出す際のポイントについてのお話で、具体的には「コンセプトの共有」という切り口で書かせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
このテーマは、私がJリーグ チェアマンの村井さんと対談をさせていただくことが決まった時から、お話ししてみたいことのNo.1でした。もしこのコラムをご覧いただいている方でまだ村井チェアマンと私の対談をご覧になっていない方がおられたならば、ぜひともこちらの見逃し配信からご覧ください。お時間のない方で「コンセプトの共有」に関する部分だけとりあえず見ておきたいという方は、だいたい開始から25分くらい経ったところからこのテーマについてのお話が始まりますので、そこだけでもご覧いただくと良いと思います。
村井チェアマンは臨時チームにおけるコンセプトの重要性についてこんなことをおっしゃっていました。「(サッカー日本代表のような臨時チームにおいては)チームのコンセプトっていうのを、しっかりリーダーが示して、全員に伝えることを徹底」しなければいけない。それがないと「(メンバーである選手が)自分の持ち味で代表に呼ばれても何をして良いのかわかんなくなっちゃう」と。そして臨時チームにおいては「(技術・戦術などの練習よりも)コンセプトの徹底に時間をかける」ことが重要だ、と。全くその通り。完全同意です。

サッカー日本代表のような臨時チームにおいては、「コンセプトの共有」がより必要になってくる/Getty Images
一人ひとりの人生に優先順位がある
臨時チームつながりで私の経験談を少し。私は大学を卒業したのち、35歳までの13年間を高島屋という百貨店で過ごしました。入社から6年間はデパ地下を中心に働いていたのですが、特に1996年10月の新宿店の開業準備がとんでもなく臨時なチームでした。私は惣菜売場の担当だったのですが、そこは約400人の販売員で構成されました。
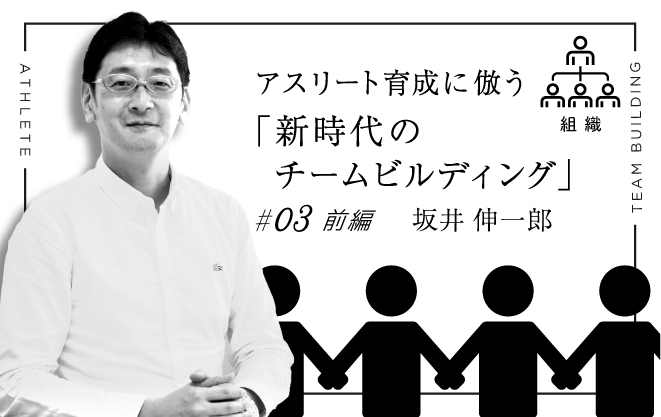
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜