ベストセラー『スラムダンク勝利学』の著者で、応用スポーツ心理学をベースに多数の企業やプロスポーツでの人材育成に貢献してきたスポーツドクター・辻秀一氏。スポーツからビジネスシーンにも応用できる「揺らがず、とらわれず」の心を自ら整えるためのライフスキルの磨き方を連載形式でお届けしていく。
目次
非認知能力と認知能力の違い
非認知能力とはこれまでも触れてきましたが、見えない質、特に心を大事にできる能力を言います。認知的能力の反対というか認知にあらずの能力になります。
認知能力とは通常のわたしたち人類が文明を発達させてきた動物とは違った特に人間固有の脳の力になります。すなわち、結果を生み出すためにどのような行動をしたらいいのか、を考え実行させる能力です。
さらに外界、環境や出来事や他人との接着を高めて、その情報を行動や結果のために利用していくのです。極めて優れた脳力といえるでしょう。さらに、人間だけが言葉を有していて、意味づけをしていくという離れ業を人間の認知脳はやってのけます。
例えば、誕生日を特別の日だと思います。朝5時を早いと意味づけするのです。雨が降ると憂鬱だと意味を付けるのは人間だけなのです。誕生日に朝5時起きの仕事があり、その日が雨だったらどうでしょうか? 最悪という意味付けを認知脳はどんどんとしていくのです。
認知脳の「意味づけ」のメカニズム
そもそも認知脳の意味づけは生命維持のため行われてきました。ライオンを見たらヤバいと意味づけするから逃げられたのです。がしかし、この脳はどんどん進化し、生命維持以上の結果を生み出すために、意味に溢れるようになったのが現代社会です。
すなわち、人は認知脳があるので意味で動き、しかも生命維持のために元々のネガティブな意味づけをする習性だけは変わらないので、さまざまな負の感情を抱えてストレスの海の中で溺れているのです。
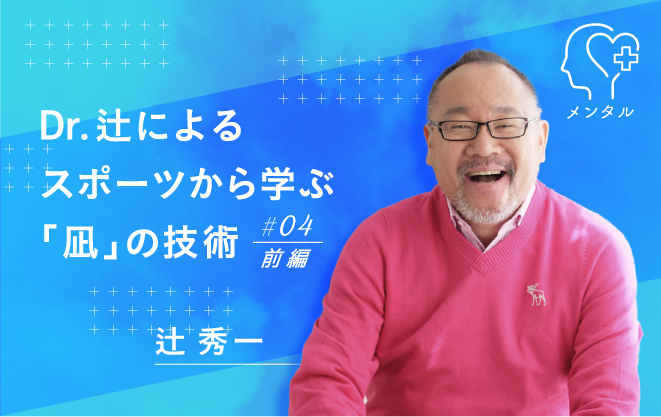
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜