アスリートの競技成果を向上させる座学プログラムを、ビジネスなどあらゆる分野の人材育成メソッドに体系化した「スティッキー・ラーニング」を開発した坂井伸一郎氏。「絞って伝えて、反復させること」をポイントに、多業種のビジネスパーソンを 「戦力」に変えてきた人材育成のプロが、時代の変化に適応するチームビルディングの在り方についてお届けしてきた連載も今回で最終回。コロナ禍により激変した世界におけるチームビルディングの在り方と未来について解説します。
ニューノーマルのビジネスシーンで直面する難題
こんにちは、坂井伸一郎です。アスリート育成に倣う「新時代のチームビルディング」というテーマでコラムを書かせていただいておりますが、今回が最終回となりますのでここまでのお話を少し整理させていただきますね。
まずこのコラムの出発地は、今年4月17日に公開されたJリーグ チェアマンの村井満さんと私とのオンライン対談です。「結果を出すチームビルディング」をテーマに約60分に渡りお話をさせていただいたのですが、その中で村井さんは2つのキーワードを挙げておられました。ひとつは「“臨時”チームのチームビルディング」という視点、そして2つめは「コンセプトの重要性」です。ですので前回および前々回とこの2つのキーワードに対して村井さんのお話を振り返りながら、私の考察をコラム仕立てで書かせていただいてきたわけです。
では最終回はどう締めくくろうかと考えました。考えて出した最終回のテーマは「ニューノーマルのチームビルディングにおける、時間と空間の超え方」です。
今、主にビジネスシーンにおいてチームビルディングを必要としているみなさんは、二つの難題に直面しているはずです。
多数の世代の塊が同時に存在する時代
一つ目は「コロナ禍による仕事環境の変化」です。これはテレワークが増えているということに止まりませんよね。会議は縮減され、机を並べて仕事をしていれば自ずと生じていた隙間時間のコミュニケーションも躊躇われる状況。飲食を伴う会食(接待や飲みニケーション、自宅に同僚を招くなど)や業務時間外の懇親(休日を利用した会社イベントや仲間同士でのハイキングや小旅行など)は、やったら場合によっては懲戒のリスクがありますし、外出同行の際の「軽くお茶していこうか」や「飯食ってから事務所戻るか」も激減しているでしょう。
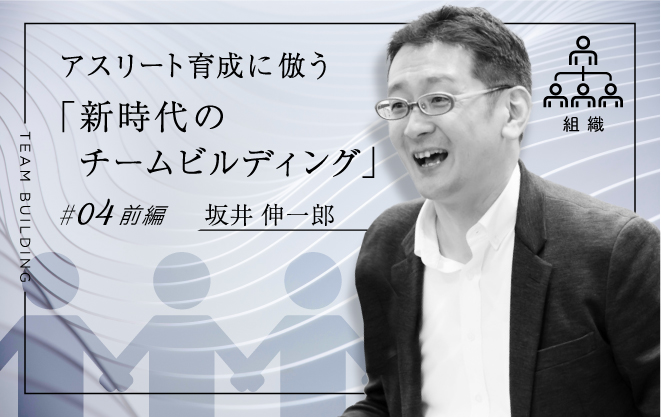
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜