自身の引きこもり経験克服を機に独自のコーチングメソッドを開発し、多数の企業経営者、アスリートなどのカウンセリングを務める中島輝氏。ベストセラー『自己肯定感の教科書』の著者であり、“自己肯定感の第一人者”として注目を集める人気カウンセラーが、社会で生き抜くために必要な実践的な技術を連載形式でお届けする。
写真/川しまゆうこ
目次
スポーツで分泌される神経伝達物質が「ストレスに強い心」をつくる
スポーツが心に与える好影響には、自己肯定感を高めてくれることの他に、「ストレスに強い心をつくってくれる」ということも挙げられます。このことには、スポーツをやることで分泌が促される、「ノルアドレナリン」「ドーパミン」「セロトニン」という3つの神経伝達物質がかかわっています。
◆ノルアドレナリン
ノルアドレナリンは、ストレスを感じたときに分泌される神経伝達物質です。交感神経の活動を高める働きを持ち、活動意欲が湧いてモチベーションが高まります。
◆ドーパミン
ドーパミンは、「快楽のホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質です。ドーパミンが分泌されると、人間は快楽を感じて「もっと楽しいことをしたい!」とポジティブな感情を持ちます。
◆セロトニン
セロトニンは、脳にあるストレス中枢を鎮めてくれる神経伝達物質です。ノルアドレナリンとドーパミンの分泌を制御する働きもあり、精神をフラットな状態に導きます。
3つの神経伝達物質は、「活動意欲とモチベーションを高める」「ポジティブな感情を持たせる」「精神をフラットな状態に導く」というかたちで、それぞれがストレスに対処してくれます。日常的にスポーツをやることでこれらの神経伝達物質が分泌されやすくなるため、ストレスに強い心がつくられるのです。
スポーツがビジネスパーソンにもたらすさらなるメリット
ここまで、スポーツが心に与える好影響、スポーツが育んでくれるマインドについて解説してきました。それらのマインドが、ビジネスシーンにおいても有用なものであることはいうまでもありませんよね?
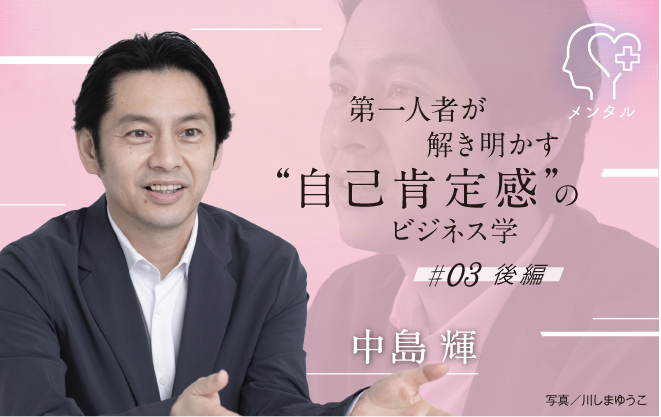
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜