ビジネスの戦略決定や市場分析のほか、政治など多分野で応用される「ゲーム理論」を専門に、アメリカの名門大学で教鞭をとる鎌田雄一郎氏。社会において複数の人や組織が意思決定を行う場合に、どのような行動が取られるかを予測する「ゲーム理論」のスペシャリストは、トップアスリートの思考をどう解析するのだろうか。「bizFESTA」にて、 WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太選手と対談した鎌田氏。若き天才ゲーム理論家が、たった一度の対談を基に<王者の意思決定>に至るメカニズムを複合的な視点でひもといていく。
4月16日 – 18日に開催されたSPODUCATIONのイベント「bizFESTA」にて、プロボクサーで現WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太選手と対談をした。初回の記事では、私の専門であるゲーム理論について説明しながら、この対談を概観した 。
前稿からの数回は、対談内容の細かいところを振り返りつつ、私なりの気づき を加えていっている。本稿は、その第二弾だ。
対談を振り返ると言っても、対談内容の全ては書ききれないし、私の筆力で村田選手の発言のニュアンスを正確に伝えきれているとは限らない。なので、この記事を読んで興味を持たれた方は、ぜひ見逃し配信をご覧いただきたい。
100点を出そうとするから、負ける
村田選手と対談をしていて、高校生の頃を思い出した。
「満点を取らなくたって、東大には受かる。絶対できる問題を、ミスしないように解け。それだけで、十分だ」
大学受験を控えた高校三年の時、化学の先生が口を酸っぱくして言っていたのだ。なぜ先生がそんなことを言ったかというと、それは「完璧を狙ってつい難しい問題に時間を使ってしまうと、結局解けない確率が高いし、他の確実に得点につながる簡単な問題に時間を使うことができなくなってしまう」からだ。
村田選手も、文脈は違えど、同じことを言っていた。
前稿で触れたように、ボクサーが崩れる時に一番多いのは、「自分から崩れる」ということらしい。そう聞いたので、「ではどのように準備をすれば、自分から崩れることのないようにできるか」という質問をぶつけた。その回答は、
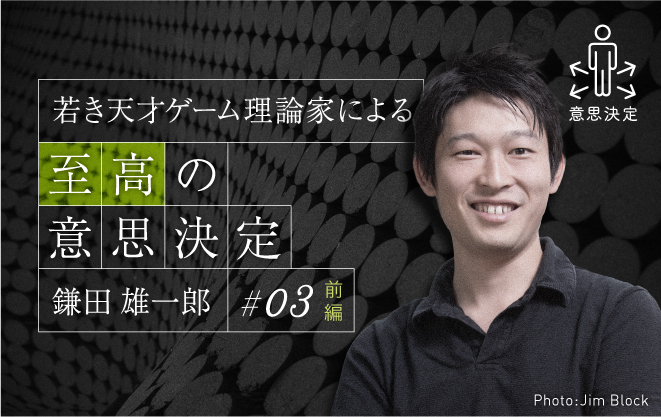
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜