ビジネスの戦略決定や市場分析のほか、政治など多分野で応用される「ゲーム理論」を専門に、アメリカの名門大学で教鞭をとる鎌田雄一郎氏。社会において複数の人や組織が意思決定を行う場合に、どのような行動が取られるかを予測する「ゲーム理論」のスペシャリストは、トップアスリートの思考をどう解析するのだろうか。「bizFESTA」にて、 WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太選手と対談した鎌田氏。若き天才ゲーム理論家が、たった一度の対談を基に<王者の意思決定>に至るメカニズムを複合的な視点でひもといていく。
考えるな、感じろ!
そう思い、これら諸々のゲームの例について話した後、村田選手に聞いてみた。「ボクシングで勝敗を分けるのは、何か?」というのが質問だ。より相手を読んだ方が勝つのか? パンチが強いと勝つのか? それとも何かしらの「センス」が優っている方が勝つのか?
最初に村田選手が言ったのは、
「将棋とボクシングの大きな違いは、ボクシンングにおいては考える時間がないことだ」
ということだった。
まず、村田選手がボクシングを(ジャンケンや◯×ゲームではなく)将棋と比較したのは、おそらくボクシングにおいてもやはり相手を読み切ることが不可能なものだと考えているからであろう。
これは納得できる。3分×12ラウンドでの攻防には、(まさに将棋のように)無数の試合運びの可能性がある。これは他のスポーツ──例えばサッカー──でも同じで、ボクシングも、いくら世界戦だといってでも「読み合いの完了したゲーム」とみなすのには無理があるだろう。
さて、将棋とボクシングを分ける「考える時間」だが、たしかにこれはボクシングというゲームの特殊性と考えられる。他のスポーツと比べても、特に反応スピード・一瞬の判断や意思決定が重要となるスポーツだろう。
だから、ボクシングにおいては、ブルース・リーの言うように、「Don’t think. Feel!(考えるな、感じろ)」で行動を瞬時に決定していかなければならないのである(村田選手のブルース・リーのモノマネをまだ見ていない人は、見逃し配信をチェック!

2019年7月のロブ・ブラントとのリマッチは、練習の段階から始まっていた。「0点」と振り返る前戦から「50-60点」の動きを発揮し完勝を納めた /Getty Imeges
メンタルの安定と、瞬時の判断
単なる読み合いではなく、そこに「考える」だけでは完成されない「瞬時の判断」という要素が加わるというのは、ボクシングの醍醐味であろう。
では「瞬時に感じて動く」ためには、何が必要か。
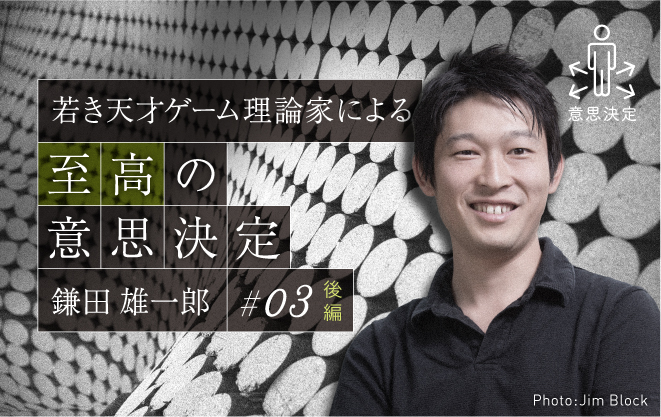
RECOMMEND
前の記事
<8・17北海道開催>日本指導者協会(JFCA)
子どもの自主性を高めるトレーニング論と試合環境 〜欧州育成事情〜
次の記事
<8・31新潟開催>日本指導者協会(JFCA)グラスルーツ普及事業指導者研修会
指導⼒に⾏き詰まった⼈必⾒! 指導⼒ワンランクアップ研修会〜サッカーで苦しむ⼦を1⼈でも減らすためのトレーニング論〜