個々の性格診断から人間関係を科学的に分析し、最適な組織編成・開発に応用する『FFS理論』にて、数多の組織・人材の活性化を支援してきた古野俊幸氏。この理論をもとに人気漫画の登場人物を題材に解説した『ドラゴン桜とFFS理論が教えてくれる あなたが伸びる学び型』を上梓し、注目を集めている。企業だけでなくプロ、大学スポーツの組織編成も支援してきたエキスパートが、FFS理論をベースにスポーツから日常に応用できる自己分析、チーム編成の考え方を連載形式でお届けする。
思考の特性は「凝縮性」「受容性」「弁別性」「拡散性」「保全性」の5因子に分類されるFFS理論の概要はこちらの記事をチェック!
目次
良いチームとは良い議論プロセスにあり
チームで仕事をする人にとって、「良いチーム」との出会いが求められますが、チームを評価する指標を持っていない人にすれば、何が良くて、何が悪いのかがわからないことがあります。
弊社では、意図的にチームを組んで、チームとしての「意思決定」ゃ「創造性開発」のためのエクササイズを体験していただきます。
チームとしての議論を終え、意思決定した内容とプロセスを報告していただきますが往々にして「我々のアウトプットは良かった」「良いチームであった」と語るのです。
もちろん、自分たちは手を抜かずに〝精一杯〟やったことだと思いますが、チームとしてのアウトプットが良かったのか疑問に思うことが多々あるのです。
それは、議論プロセスに原因があるからです。
賛成と反対の立場を明確にすることで論点が明確になる
良い議論プロセスを整理してみましょう。
一つの議論テーマがあるとしましょう。
賛成と反対の立場を明確にすることで、議論すべき論点が明らかになります。「イシュー」と言われるポイントですね。それぞれが、なぜ賛成なのか? 例えば「メリットが〇である」と主張します。その主張に対して、なぜ反対なのか? 例えば「デメリットが□である」です。そのメリット、デメリットを議論することで、論点が明確になり、対立を乗り越えようと建設的なやりとりに発展し、「一人では考えられなかった解決策が生まれる」。これがチームとしてのシナジーです。
「対立」を避け“皆の顔を立てる”のが良い議論?
しかし、多くのチームは「合意を図る」ことに終始します。
ワークの進め方は、最初に個人で考えて「自分の答え」を出していただきます。次にチームで集まりチームとしての合意=意思決定をしていただきます。
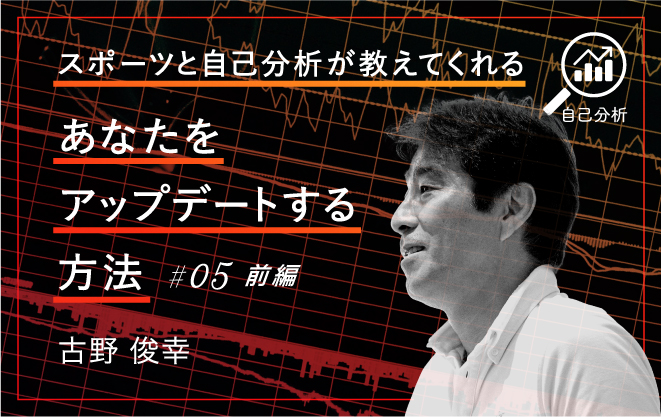
RECOMMEND
前の記事
サイトリニューアルのお知らせ│HOW TO USE NEW WEB SITE