アスリートの競技成果を向上させる座学プログラムを、ビジネスなどあらゆる分野の人材育成メソッドに体系化した「スティッキー・ラーニング」を開発した坂井伸一郎氏。「絞って伝えて、反復させること」をポイントに、多業種のビジネスパーソンを 「戦力」に変えてきた人材育成のプロが、時代の変化に適応するチームビルディングの在り方について、連載でお届けしていく。
具体的すぎず抽象的でもない「コンセプト」の意味
臨時チームの場合、お互いにそんなに良くわかりあっているわけではなかったり、共通言語や共通理解がないということがほとんどだったりします。でもチームとして集まり、チームであるが故にそこにミッション・ゴールがすでにある。往々にして臨時チームには時間の猶予がない。となると「まずはお互いを理解し合うところから始めましょうか」なんていう悠長なことはやっていられない。そんな時に一番重要なものはなんなのか? というのが私が村井チェアマンとお話ししたかった、そして実際にお話しできたことでした。
その答えが「コンセプト」だったということです。
コンセプトとはそもそもなんなんでしょうね? ……辞書で調べると「概念」とか「全体を貫く基本的な観点・考え方」と出てきます(グーグル日本語辞書 Oxford Languagesより)が、これだとなんだかよくわからなくって、仕事で使いこなすことは難しいと思います。私の肌感覚で申しますと、目標のように具体的なものではなく、理念のように抽象的なものではないもの、というイメージです。これでもまだあやふやですね。

2019年のW杯で日本を熱狂させたラグビー日本代表。コンセプトを徹底し、“ワンチーム”の結束力でいくつもの奇跡を起こした/Getty Images
理念と現場のギャップを埋めるコトバ
「パターン・ランゲージ」と呼ばれる1970年代に建築家クリストファー・アレグザンダーが街づくりや建築のために提唱した知識記述の手法があります。
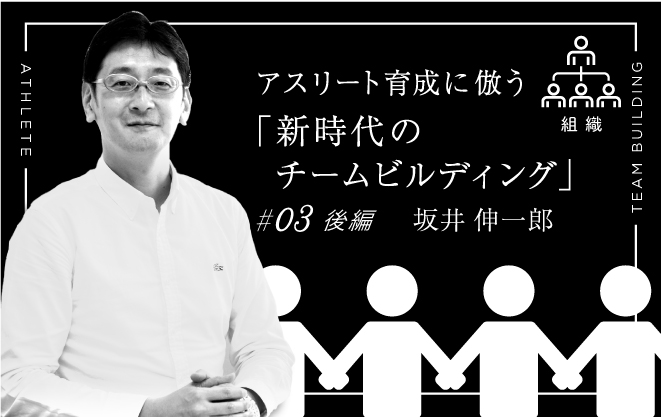
RECOMMEND
前の記事
サイトリニューアルのお知らせ│HOW TO USE NEW WEB SITE