ビジネスの戦略決定や市場分析のほか、政治など多分野で応用される「ゲーム理論」を専門に、アメリカの名門大学で教鞭をとる鎌田雄一郎氏。社会において複数の人や組織が意思決定を行う場合に、どのような行動が取られるかを予測する「ゲーム理論」のスペシャリストは、トップアスリートの思考をどう解析するのだろうか。「bizFESTA」にて、 WBA世界ミドル級スーパー王者の村田諒太選手と対談した鎌田氏。若き天才ゲーム理論家が、たった一度の対談を基に<王者の意思決定>に至るメカニズムを複合的な視点でひもといていく。
本分とアウトプットのタイムマネージメント
村田選手にアウトリーチ活動の位置付けを尋ねたところ、彼にとってYouTubeチャンネルは、「SNSのような感覚」とのことだった。自分の考えを発信したり対談をして様々な考え方を引き出したりする場であり、視聴者に「いい影響を与えられれば」 と思って取り組んでいる。
しかし、だからと言って、情報発信は決して自分のメインではない。パフォーマンスの向上を目的にして発信しているのではないのだ。競技に影響が出るようなメディアの露出の仕方などは全くするつもりはない。ただ発信自体にネガティブ要素はないので、線引きをしっかりした上で、競技や後進のためになるようなことならばやることにしている。ボクシングの練習にできるだけ時間を使い、余った時間でアウトリーチ活動をしている、とのことだった。
こういったスタンスは、至極当たり前に聞こえるかもしれない。しかし、この「本分とアウトプットのプライオリタイズ(優先順位づけ)」は実は難しいことである。村田選手自身も、2018年ブラント戦第1戦の前はボクシングの練習以外の仕事が忙しく、集中し切れていなかったと話す。これと同じ轍は踏まないように、今はタイムマネージメントに気をつけているとのことだった。
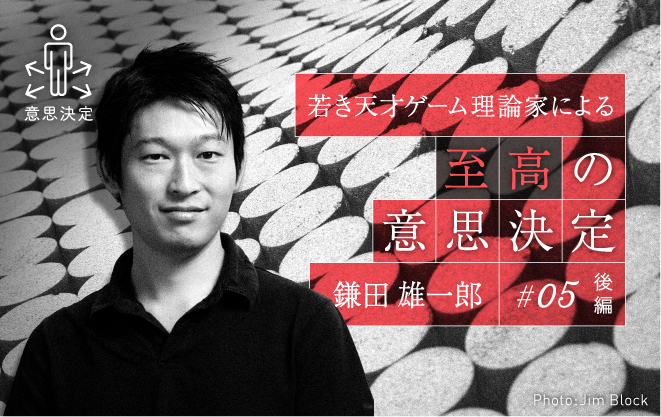
RECOMMEND
前の記事
サイトリニューアルのお知らせ│HOW TO USE NEW WEB SITE